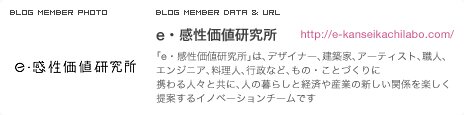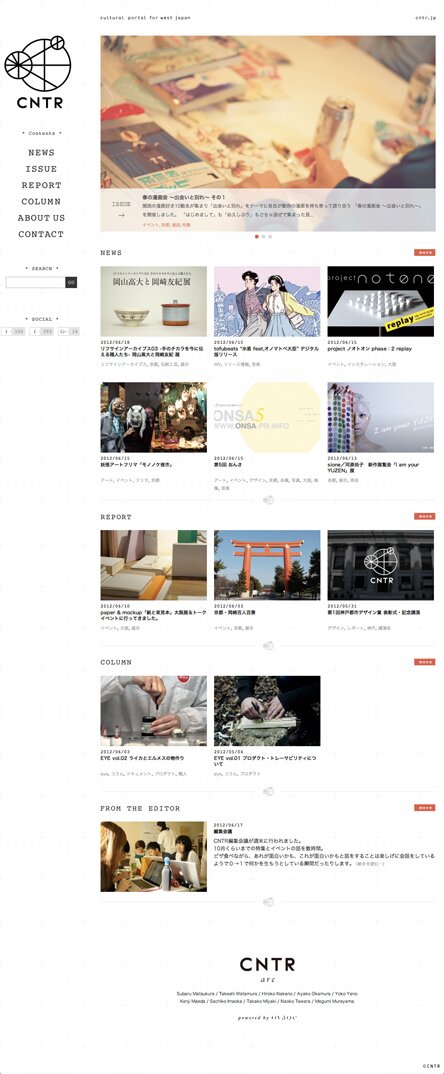Hear 15 米原 有二に聴く

今回、お話をお聞きしたのは、京都の若手職人と、その手仕事を紹介するプロジェクト「リフサイン・アーカイブス– 手のチカラを今に伝える職人たち –」で監修を行って頂いているライターの米原有二さんです。2005年に個人事務所sakura editorial works.(サクラエディトリアルワークス)を設立し、京都を拠点に伝統工芸・伝統文化を対象とした取材・執筆活動を行っている米原さんに、伝統工芸に 関わるようになった経緯、それまでの思いなどをお聞きしました。
「リフサイン・アーカイブス– 手のチカラを今に伝える職人たち –」
〜潜在的に「欲しいと思っている人物像」を導き出すということの面白さに気付いたんです〜
> ライターという職業を選んだ最初のきっかけについて教えて下さい。
大学4回生の時に僕は単位が足りてなくて、夏休みにある集中授業をとりあえず全部取っていたんです。授業の内容にはほとんど興味がなかったんです が、その中の一つに「広告」の授業があって、講師として広告代理店で働く人やクリエイターなど、広告制作に携わる人が来ていろんな話をしていたんです。その中にアメリカと日本の広告比較論を話す人がいて、それがものすごくおもしろくて、そのことがきっかけで広告の世界に興味を持ち始めました。
それで大学を卒業して初めて就職したのが求人広告の仕事だったんです。そこでは営業をして、クライアントと一緒に企画を考えながらコピーを書いて広告を作っていました。その中で自分がもっとも楽しいと感じた作業がクライアントと折衝することでした。担当者が潜在的に「欲しいと思っている人物像」から、具体的に「必要な人材」を導き出すということの面白さに気付いたんです。そこでは約3年間くらい働いていたんですが、あてもなく辞める事になって、次はネットで偶然見 つけたベンチャー新聞社に入る事になりました。規模はとても小さくて、動く人が僕を含め2人だけだったんです。
記事を全部ネットにアップしたりと、当時(2005年)では他のメディアにはない、新しい感覚でやっている所で、2年半程お世話になりました。そこでは書く事はほとんどしなくて、僕は編集担当で、もう1人は取材して記事を書く記者さんでした。
> どんな取材をされていたんですか。
大手だったら経済部なら経済の事、文化部は文化の事って決められているけれど、ベンチャー新聞なので制約がほとんど無く、何でもやっていましたね。記者と伴走する形で、何が面白いのか、要は何がニュースなの?という事を記者と話をして、自分達でネタを見つけて、取材先を決めたりしていました。
例えば、企業の新製品発表の取材をした足で、現代美術に関わるギャラリーなんかの取材をしたりしていたんです。

〜それでどう変わるかが書けないと僕らの存在価値なんて無いわけですよ〜
> 大手の新聞社との違いみたいな事は意識されていましたか?
物事の事象を書くだけ、ということはしないでおこうと考えていました。記者の人と話をしていて、例えば、企業の新製品の発表会に行くと大手の新聞社もその場にいて、どこも同じ事を書くことになります。
でも、生活している人にとって大事なのは、新しい商品が出来た事によって何が変わるかって事だと思うんですね。テクノロジーが進むというのは事象が起こっただけで、それで世の中がどう変わるかが書けないと僕らの存在価値なんて無いわけですよ。だから、そこの部分一点を強く意識して突き詰めていましたね。
> そこから伝統工芸に関わる事になった経緯についてお聞かせ下さい。
新聞社を辞める直前に京都の伝統工芸について取材する機会があって、そこで調べているうちに今の伝統産業が置かれている危機的な状況を知ったんです。それをきっかけに京都の職人さんを取材するシリーズを新聞の紙上で始めようという話になったんです。
最初は、西陣にいる西陣織の木製の杼(ひ)を作っている日本で一人だけの職人さんの所にインタビューに行ったんです。よくある職人紹介という形ではなく、その職人さんがどういう風に生きてきて、現在はどのような経済事情なのかといった普通ではあまり突っ込まないような取材をやっていました。それが、何回も通って、書き直したりして、苦労してやっと載ったんですよ。それで、次にどこに取材へ行こうかという時に会社の事情で退職することになったんです。
でも、自分の中で動き出した伝統産業についての「モヤモヤとした問題意識」をうやむやにしたらあかんという気持ちがあって、一緒に辞めた記者と二人で取材活動を行える場所を借りようという事で、事務所をハイネストビルに借りたんです。
おたがい、良いキリだと思う所まで取材して書こう、それがどこに載るあてもないけど、とにかく納得出来る所までやろうと話しながらやっていましたね。でも、取材して素材を持ち帰って、あれこれと言っているけど、締め切りがあるわけじゃないから、やっぱり書かないんですよ(笑)。
そんなどうもならない時期がありました。そんな時に人の紹介で京都造形芸術大学の先生と話をする機会があって、その時に思いの丈を一生懸命に話したんです。 そうしたら、その先生が「意義のある事だから今みたいにあてもなく取材しているのはもったいないよ。ちゃんと世に出さないといけないんじゃないかと」言ってくれて、大学の調査研究に加えてもらえる事になって、そこで初めて役割が与えられた感じですね。
> フリーペーパーを作ろうとされていた時期はその頃ですか?
そうですね。その頃は、出す先の無いフラストレーションでいっぱいになってしまって。取材は楽しいけれど、書く行為はちょっと辛い部分が多い、でも、インプットばかりして、アウトプットしないのが続くと凄く苦しいんですよ。それまで締切に追われてて、嫌でもアウトプットしないといけない状況から、期限が無くなって、書いてもいいんだけど、書いた所で誰の目にも触れない。 そんな中で、段々、自分が取材して咀嚼した事を世に出して、人に読んでもらいたい欲がパンパンになって来ていて、それで自分達で媒体を持ったらいいんじゃないかって話になって、フリーペーパーって形を考えたりしていましたね。
でも、二人で話をしていてタダって事が嫌だとなって、食べられるかどうかは別にして、少しでも取材対価としてお金を貰わないと、今、職人さんが置かれている状況と同じになってしまう。職人さんが良い仕事をしても対価が安く、一生懸命に働いてもワーキングプアになってしまうような状況があって、自分達はそれをひとつの問題意識として持っているのに、自分の活動もそこに陥ってしまえば、本末転倒だと・・・。
やっぱりやるならば広く人目に触れる雑誌や本になる事を目指して、次の取材活動が出来る位のお金は回る仕組みは考える必要があるんじゃないかと話していました。
その頃は暇なので、本になった時にタイトルどうする? とか言ってましたね(笑)
その時に人の生き方って手に出るから“手のひら”という言葉は入れたいと話をしていて、だから、最初に出した本の『京都職人』のサブタイトルが“匠のてのひら” なんですよ。晴れて世に出たのは、そんな話をしていた時から2年後のことですけど(笑)
> 今のように自分で書き出したのはいつからですか?
大学への研究報告書が完成する前に、一緒に取材をしていた記者さんが就職する事になって、それから長さや内容がバラバラな粗原稿を報告書としてまとめるのに、ほぼ書き直しに近いことを自分がやらないといけない状況になって、それで初めてまとまった量の原稿を書くという作業をしたんです。そこからまた『京都職人』を出す事が決まった時に、報告書の原稿から記事を半分以下に直してほしいと言われて、ほぼリライト的な作業が半年間に二度くらいあって、ボリューム的には本を二冊書き下ろすくらいの作業でしたね。
そうした作業の中で、ここ聞いてないやんっていう部分が出てきたりする事があって、ほぼ全件の職人さんにもう一度取材をすることになって、そこで1人で取材に行って、1人で書くという事をやるようになったのが今の土台になっています。 その時は、短い期間でやらないといけない状況だったんで必死でやってましたね。今考えれば、色んな雑誌に書くことや、フリーのライターとしての活動は、『京都職人』が本になってからなんですよ。それまでは大学の外部研究員みたいな立場で、他の事は何もしていないし、本が出版されてからまたやる事が無くなって、そこで初めて「あぁ自分は“フリー”なんだ」と感じました。

〜「ライフワークにしなさいよ」と言われたんです〜
> フリーでやっていく事への迷いは無かったですか?
その時は「フリーでやっていくぞ」とか「やっていける」とは思っていなくて、それこそちょっと前に初めて自分で取材して全部自分で書くという体験をしたばかりだったので、「雑誌で出来るわ」なんて思ってないわけですよ。だから就職を考えていたんです。でも、当時27歳で、本当にお金の事や生活の事を抜きにして、自分がしなくちゃいけないんだという事を、やり終えた後だったので、就職先にもそういうのを求めてしまうんですよ。
「それを本当にしたいの?」という事を。
当たり前の事だけど、それまで気の向くままに取材している事を思えば、どこに行っても制約される自分が思い浮かぶんですね。それでそんなんじゃなく、漠然と「もう少し続けてみようかな」と思ったんです。大学の先生とも話をしていて、職人さんの取材は同じテーマであっても、色んな切り口で続けて積み重ねていく事が君自身のアーカイブにもなるし、5年、10年取材を続けてる人の言葉じゃないと深みを持たせたり、説得力を持たせられないから、「ライフワークにしなさいよ」と言われたんです。
「取材をさせてもらう職人さん達にとっても、ふらっと来て、“今、伝統工芸の取材してるんです”という人よりは、色々な所を取材して、あなたの所でこんな事が聞きたいんですという人は厚みも違うし、答えてくれる言葉も絶対違うはず」というような事を言ってくれて、そこでひとつ自分の中でストンと納得出来ました。でもまだ、“どうしよう”と思ってたんですけどね。(笑)
そうこうしているうちに京都の職人とか伝統工芸についての雑誌の仕事が入って来たんです。僕がしたい事を企画に出して、良かったら動いて原稿にして、それはそれでやりがいを感じて、決断する以前にフリーのライターになっていった感じですね。周りからもそう見られるようになったし、それまではライターって名乗ってなくて、名刺に肩書きをどう入れていいのか分からなくて、なんやろと思って「伝統工芸の取材を熱心にしてる人」というポジションを勝手に位置づけて(笑)やってました。
そうやって周りの流れに巻き込まれ、その流れに身をまかせる形でライターとしてかたちになっていきました。

〜他にやっている人がいないから自分が見過ごしたら埋もれてしまうという事が原動力で次にも行ける感じがする〜
> 今やっている仕事の先にある理想の形ってありますか?
これから先の自分というのは特に無いんですよね。
今まで濁流に飲み込まれてやって来ていて、伝統工芸の取材の事で、“こういう事がしたい”、“ここまでしたい”というのはあるんだけど、環境を作ったり、この雑誌に絶対書きたいとかも無かったし、今もそんなにありません。
“もうやる事無いな”と思えたら辞められるんだけど、やっぱり“終わってない”んですよ、取材が。
ちょっと話が戻るんですけど、『京都職人』が出て一年後くらいに、京仏壇・京仏具の取材を始めたんです。それでその時に締め切りまでの余力が残ったので、何をしようかとこれまでの工芸の取材を振り返ってみたら、職人さんが「最近ええ材料無いなぁ」とか「ええ道具無いなぁ」というのを色んな所で聞いた事を思い出して、その時に「道具と材料」というテーマで10件くらい取材したんです。
その時に漆でいうと漆の木から漆を掻く人がいて、採れた漆を精製する職人さんがいて、精製の仕方で黒、赤、白の色を作ったりと、そこには面白い世界がいっぱい広がってるなと思ったんですね。 あと、問題意識として、伝統工芸のきらびやかな部分にまだ人の目は向きやすいけど、それを支える道具や材料を作る人にも後継者がいない事は見失いがちなんです。でもその人達がいないと工芸は何も出来ないんです。それで「これはあかん」と思って、今、蚕を育てて絹糸を作る人や、表具に糊を塗るハケを作る人など、道具と材料をテーマに取材をしているところです。伝統工芸の取材を続けているのは、面白いと思う興味はもちろんだけど、取材者として言うと「問題意識」なんですよ。何とかしないとアカンやろと、他にやっている人がいないから自分が見過ごしたら埋もれてしまうという事が原動力で次にも行ける感じがする。次に取り組むことが見つからないって事は無いんだけど、もしそうなったら、それは自分の取材の未熟さ、足りなさだと思う。
“見つかるから次に行ける。どれから取材しようかと考えるくらいで、今まで次やる事に悩んだ事が無い”
> いい言葉頂きましたね(笑) でも、動いていると興味が尽きないから続けているというのは、理由として凄く力があるなと思いました。 最後に一緒に企画しているリフサインアーカイブスに期待する事を聞かせてください。
伝統工芸は、デザインやプロダクトと違って、今の生活に直接関係ないという意識があるからだと思うんだけど、無意識に線引きされている感じがするんですよ。でも、京都は特に知ってる知らないを別にして、隣の家に伝統工芸に関わる人がいたりするんですね。看板は上がってなくても、家の中で蒔絵を塗っていて、それが有名なお寺や神社の装飾の一部になっていて「綺麗やな」と思ってたりしてるんですよ。もっと言えば、現代的な生活に少し関わりがあったりもします。
例えば、折りたたみ携帯電話のヒンジ(丁番)に使う電解板を薄くする技術があったからこそ折りたたみが可能になって、携帯電話のデザイン領域が広がったという事があるんだけど、それは金箔を薄くする技術を近代化する事で出来た技術が採用されているんです。そういう事は結構たくさんあって、今、僕たちが便利に暮らしている事はいきなり出来たものじゃなくて、ちゃんとストーリーやエピソードがあるんですね。
そういう事って知らなくても困らないけど、音楽やデザインと同じで、知ってたらもっと楽しいというように、身近に伝統工芸を感じてもらえるようになれば面白いと思います。
|
| E KANSEIKACHI PAGE INDEX | ← Prev | Next → | |
Tweet |
今年、京都のQ-GAMESというゲーム会社とplaystation3用ソフト”PixelJunk™ Eden”というゲームをコラボレーションで制作し発表しました。私はアートディレクション、グラフィック&サウンドを手掛けました。そして、今週末なのですが、11/21 ... [more]
Refsign Magazineがリニューアルしてから初ポストです。サイトもカッコ良くなって、どんなブログ書けばいいのかな・・なんて思いながら他のブログメンバーのを参考にしようと思っていたら、皆さんも同じ作戦なのか一向にポストされる気配もなく・・・。笑先日のポストで佐野さんもTwitterについ ... [more]
関西圏の人なら知っていると思うのですが、僕の住んでいる街にはひらかたパーク、通称 “ひらパー”がある。年配の方でも「菊人形の所やな」という事で知られているので、説明をするのにとても便利だったりします。 (という前フリを書く為に菊人形を調べてみたら、1910年に初開催で、その歴史に驚き) そう ... [more]
カウンターで、知り合い3人組の真ん中の女子がオレに言いました。女・中「妄想てしはりますか?」山「妄想?しますよオレ。」男・左「フハっ、しはりそうですよね。」女・右「私、しません〜。」今日暇だったので、妄想て何か考えました。小学校時代、弟と枕を並べて寝てました。。布団入るといつもはじめるんです。。妄想 ... [more]
東京は原宿にあるオシャレな人達によるオシャレな人達のためのお店「レベレーションズ」というお店にありがたい事に我がKOG-Tシャツが大抜擢!!本日5/15より絶賛展開中でございます。お店では廃棄されたスケボーのボードを四角く切ってそれでドット絵のマリオを再現してたりと、凝った演出のディスプレイをされて ... [more]
そんな思春期らしい僕を勇気づける為に今晩は京都市SOUTHの方へ。案内は顔出しNGのT氏↓ 場所は京都駅近くの水月亭、何やら珍しい物が食えるらしいです。 先ずは名物の蒸し豚 豚の味が濃くて脂身が美味しい。続いて豚足↓臭み無し、プルプル。 ↓ガツ?だっけかな??牛の男性器に ... [more]
みなさま。。あけましておめでとうございます。今更ですが。。年末年始と尋常ではない忙しさを乗り越え、やっとこさ今日2009年の初ブログです。とは言いましても、大晦日、ジラフの鍋パに行ってきました。 アホの子です。 この子は可愛いですね。余談になりますが鍋パ(鍋パーテー)。略して鍋パです。ウ ... [more]
僕たちFLAKWORKSでは、現在、外部パートナーさんを広く募集しています。フリーランスやSOHOで制作業務をされている感じの方で、一緒にわいわい仕事ができる人たちと出会えたらと思っています。具体的なスキルとしては、・WEBサイトデザイン・コーディング・MTやWordPressの実装・FLASHのオ ... [more]
最近、週末は決まってお出かけしているんですが、この前は布を買いに大阪へ行ってきました。 行ってきたのが、4階建のビル丸々が布を中心に手芸用品が揃っているお店。 布の数もさることながら、手芸用品も豊富! 目的の布を探しながら、ワッペンコーナーに足を止められ、レースコーナーを物色したり、あっちで ... [more]
年末ですね。。オンズもさまざまな行事に使って頂いててありがとうございます。ま、主に忘年会ですか。や、なかなかお会い出来ない人がひょこっと来てくれたり、「明日からフランスです」みたいな人がいたり。。クロちゃん 芸能人級の可愛さです。彼氏はフランス人でオンズにも玉に来てました。木村カエラよりもクロ ... [more]
昨日はこのサイトでも、そして日頃からも色々お世話になっている田井さんの新しいお店、「Cafe Salon」の新風館のお店のレセプションパーティに。前々から田井さんとこの新店の話は色々としてきました。今まで、何度かお店ができる前から見せてもらっていて、段々と仕上がってく様子も見ていました。でもやは ... [more]
ワークショップ大野紅のオリジナルロゼットづくり カラフルなリボンを折りたたみ、縫い重ねて作る伝統的な技法に、くるみボタンやピンバッヂを合わせて作るオリジナルロゼット(勲章)です。 世界でただ一つあなただけの勲章を作ります。 【ワークショップ概要】 ... [more]
作家が制作するきっかけ、衝動、思いはそれぞれにあって、それを知る事でより注意深く作品と見ることが出来たり、より深く感じる事があったりする。 今回「&ART」で紹介されたいちかわともこさんは、大きな意味での「宗教」というのが、その起点のひとつにあるようです。 「宗教」というと、何か 大 ... [more]
今日は、打ち合わせに四条方面へ出たので、帰りに、「行きつけ」の大型書店に寄りました。事務所のスタッフには信じてもらえないかもしれませんが(笑)、ホント久しぶりの本屋さんです。その理由を自己分析してみると、色んな意味で、ちょっと落ち着いて来たからかな。気持ちがバタバタしてると本屋さんに行く気にもなりま ... [more]
「記憶」をテーマにしたダンス公演で音楽と音響を担当しています。昨年の7月に初演した『Groundless-ground(s)』の続編という位置づけされた作品です。 特設サイト >> http://www.veuvesjumelles.com/g-gs2/ ... [more]
お久しぶりっす。。最近ブログさぼっておりましたが、さぼってたわけではありません。ただ、不毛すぎまして、さぼっておりました。でも、はりきって行きましょう。小川君 最近、オンズでは交代で夏休みをまわしてます。オンズの一人が夏休み中は、彼が皿洗いに来てくれるというわけですね。小川君は、全く飲食経験が ... [more]
「MEET」のページの「THE KING OF GAMES」の江南さんとの対談をアップしました。普段から仲良くしているのでいきなりお話をというと照れる部分もありました。そして話の脱線具合も半端なくです。しかし今回、だからこそお話できた部分、そして前からの疑問などのより深い内容のお話が聞けたと思います ... [more]
いよいよ『京都藝術』も開催間近となってまいりました。 さて、開催前夜の31日には、インフォメーションとなる0000galleryにて『京都藝術前夜祭』を、1日には京都藝術開催の第一弾イベントとなる『SANDWICH× 仔羊同好会イベント』を行います。 みなさん奮ってご参加下さいね! &nb ... [more]
こんにちは。 さて、京都は河原町、galleryMainに行ってきました。河原町通り沿い、松原通りを少し下がったところの小林ビル2階、3階が今年2月にオープンしたgalleryMainです。 2階に上がってみると、松川さくら写真展『カイト』が開催中。 元はカフェだったそうで、空間は ... [more]
CNTRというポータルサイトがオープンしました。やっているのは仲良しovaqeの松倉くんを始め、おもしろいメンバー達。 詳しくはこちら。メンバーの紹介がされています。http://cntr.jp/aboutus/ 私もポータルサイトの運営は今年で4年目。本当に大変だ ... [more]